はじめに:なぜ今、この名著「株式投資の未来」を読むべきなのか?
株式投資の世界に足を踏み入れた人、あるいはこれから投資を始めようと考えている人にとって、数多ある投資本の中から本当に価値のある一冊を見つけるのは至難の業です。しかし、もし一冊だけ選ぶとしたら、間違いなくその筆頭に挙がるのが、ペンシルベニア大学ウォートン校のジェレミー・シーゲル教授が著した『株式投資の未来~永続する繁栄への投資戦略』でしょう。

この本が他の投資本と一線を画すのは、その圧倒的なデータ量にあります。単なる推論や個人的な経験談ではなく、200年以上にわたる米国株式市場の膨大なデータを徹底的に分析し、株式投資の根源的な真実を解き明かしている点に、その価値があります。初版は2005年ですが、「未来」というタイトルに反して、本書が示すのは流行を追う最新の投資トレンドではありません。むしろ、時代や経済状況、技術革新の波が押し寄せようとも決して揺らぐことのない、普遍的な投資の原理原則なのです。
現代社会は、情報過多の時代です。SNSやニュースサイトでは、日々刻々と変化する市場情報が流れ、短期的な株価の変動に一喜一憂し、焦りや不安を感じる投資家は少なくありません。そうした中で、『株式投資の未来』は、まさに嵐の海を航海する船にとっての羅針盤のように、私たち投資家に長期的な視点と、データに裏打ちされた冷静な判断力を与えてくれます。このブログ記事では、そんな不朽の名著から、特に重要だと考えられるエッセンスを凝縮し、あなたが賢い投資家として成功するための「必読ポイント」を、より深く、具体的に解説していきます。読み終える頃には、あなたの投資に対する認識が根底から覆され、より確固たる投資哲学が芽生えているはずです。
株のリターンはどこから来るのか?〜長期投資の真実〜
「株式投資で儲ける」と聞いたとき、ほとんどの人は、株を安く買って高く売ることで得られる利益、つまりキャピタルゲイン(売却益)を真っ先に思い浮かべるのではないでしょうか。もちろん、これも重要なリターンの一部です。しかし、シーゲル教授は、長期的な視点に立ったとき、もう一つ、多くの投資家が見過ごしがちな、あるいはその重要性を過小評価しがちな要素が、はるかに大きなリターンをもたらすことを、歴史的データをもって明確に示しています。それが配当、そしてその再投資効果です。
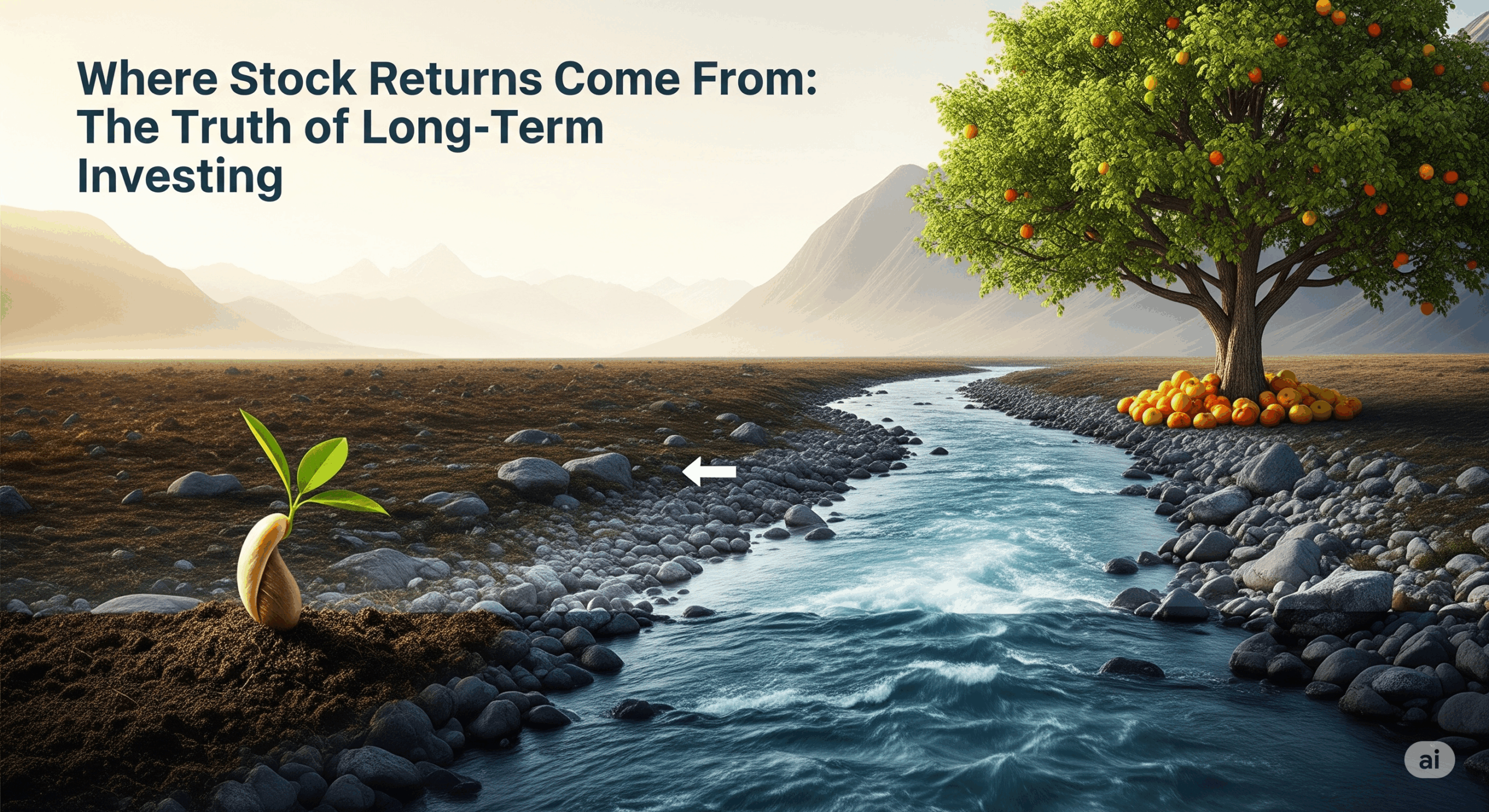
「資本の価格決定モデル」とは?:株価を動かす3つの要素
シーゲル教授は、株式投資から得られるリターンを決定する要因を、以下の3つの要素に分解して説明しています。これらを理解することが、株価変動の本質を捉える上で非常に重要です。
-
企業収益の成長: これは最も直感的に理解しやすい要素でしょう。企業が毎年安定して利益を伸ばし続ければ、その企業の価値は高まり、それに伴って株価も上昇します。例えば、新しい技術を開発して市場シェアを拡大したり、効率的な生産体制を構築して利益率を高めたりすることで、企業の収益は成長します。
-
配当利回り: 株価に対する年間配当金の割合を示します。例えば、1株1,000円の株が年間20円の配当を出す場合、配当利回りは2%となります。配当は企業の利益の一部を株主に直接還元するものであり、定期的な収入源となります。多くの投資家は、配当を単なる「お小遣い」程度にしか考えていませんが、シーゲル教授はこれこそが長期的なリターンの「隠れた主役」であることを強調します。
-
PER(株価収益率)の変化: PERは「株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)」で計算され、企業の利益に対して株価が何倍まで買われているかを示す指標です。一般的に、成長期待の高い企業ほどPERは高くなります。例えば、PERが20倍の株が30倍に上昇すれば、株価もそれに合わせて上昇します。しかし、逆にPERが低下すれば、たとえ企業収益が成長していても株価は下落する可能性があります。投資家の期待度や市場のセンチメントによって大きく変動するため、この要素は株価を短期的に大きく変動させる要因となり得ます。
この3つの要素の中で、特にシーゲル教授がその重要性を力説するのが、配当利回り、そして配当の再投資がもたらす長期的なリターンへの影響です。
配当がもたらす驚異的なリターン:軽視されがちな「再投資効果」
多くの場合、投資家は「株価が上がる銘柄」ばかりに注目し、配当は二の次と考えがちです。しかし、シーゲル教授は、1950年代から2000年代初頭までの約50年間におけるS&P500のリターンを詳細に分析し、衝撃的な事実を明らかにしました。それは、この期間における株式のリターンの約97%が、配当の再投資によってもたらされたというものです(当時のデータに基づきますが、その重要性は変わりません)。
これはどういうことかというと、もし投資家が受け取った配当金をすべて消費してしまい、元本だけで運用していたとしたら、最終的な資産は配当を再投資した場合に比べて、桁違いに少なかったということです。配当金を再投資するということは、その配当金でさらに株式を買い増すことになり、それが新たな配当金を生み、さらに再投資するという複利のサイクルが生まれます。
この複利の力は、時間の経過とともに雪だるま式に資産を増大させます。まさに「人類最大の発明」とアインシュタインが呼んだとされる複利の魔力が、配当再投資によって最大限に発揮されるのです。短期的な株価の上げ下げに一喜一憂するよりも、安定した配当を出し続ける企業の株に投資し、その配当を愚直に再投資し続けることこそが、長期的な資産形成の王道であると本書は示しています。
短期的な変動に惑わされない心構えの重要性
株式市場は、時に理由もなく大きく変動します。企業の業績とは関係なく、投資家の心理やマクロ経済のニュース、あるいは単なる投機的な動きによって、株価は上下を繰り返します。こうした短期的な変動は、多くの投資家にとってストレスの源となり、感情的な売買に走らせてしまう原因となります。
しかし、シーゲル教授は、こうした短期的な株価の変動は、長期的なリターンにとっては**「ノイズ」に過ぎないと断言します。賢い投資家は、一時的な株価の乱高下に感情を揺さぶられることなく、企業の本質的な価値(収益成長と配当)**に目を向け続けます。市場が暴落したときこそ、優良企業が安値で買えるチャンスと捉え、逆に市場が過熱しているときは、欲に駆られることなく冷静さを保つ。このような心構えこそが、長期投資で成功するための不可欠な要素なのです。株価の「ゆらぎ」に惑わされず、企業の「根っこ」に目を向けることの重要性を、本書は教えてくれます。
過去のデータが語る!株式市場の「不都合な真実」
『株式投資の未来』が投資家に与える最も大きな衝撃の一つは、過去の膨大なデータが明らかにする、私たちの常識を覆すような「不都合な真実」でしょう。多くの投資家が信じている「成功の方程式」が、実はデータ上は誤りである可能性を示唆しているからです。
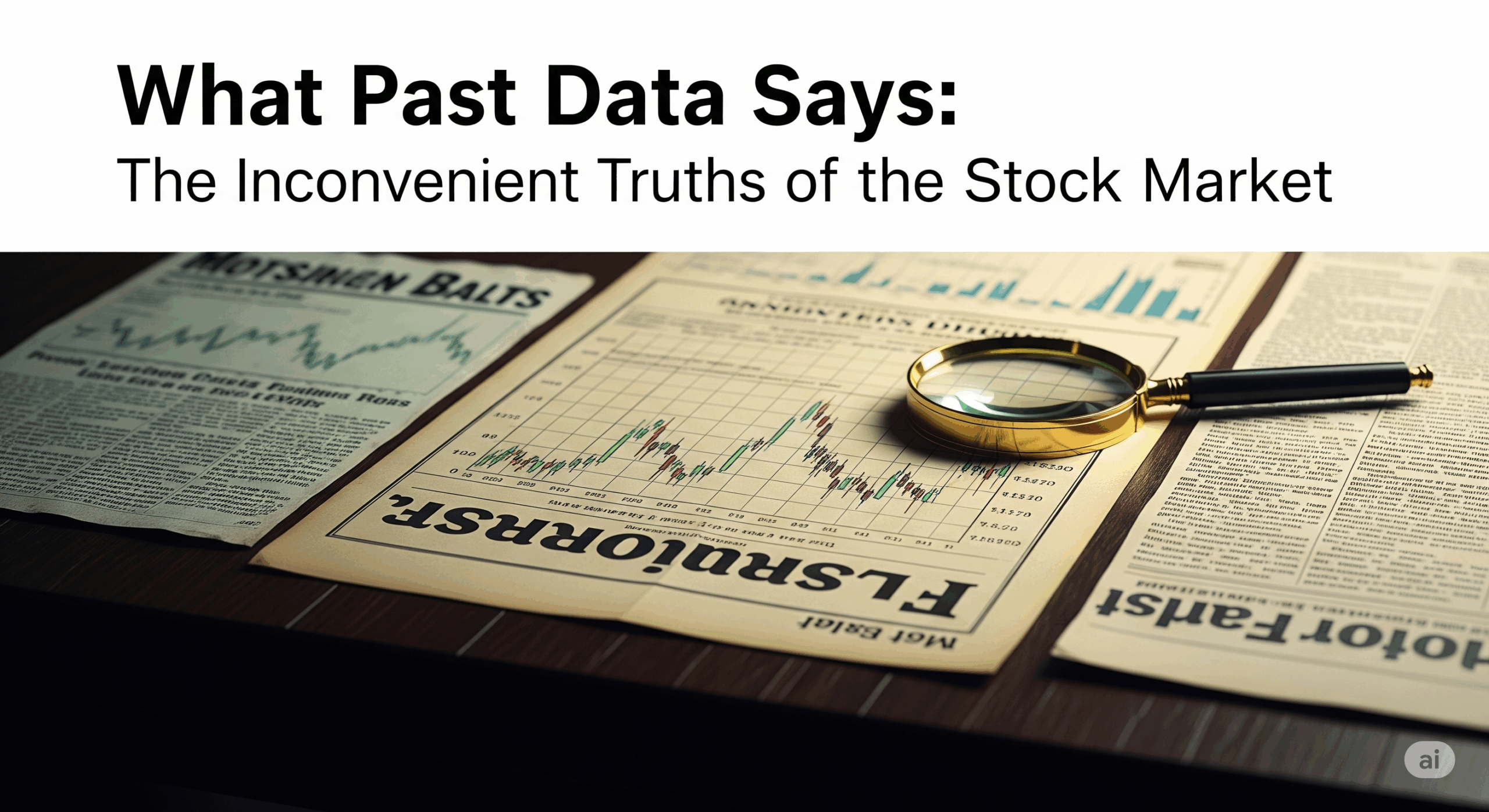
米国株式市場200年の歴史が示す驚くべきデータ
シーゲル教授は、1800年代初頭から2000年代初頭までの約200年間という、類を見ない長期にわたる米国株式市場のデータを丹念に分析しました。この分析を通じて浮かび上がってきたのは、多くの投資家が思い描く「勝ち組」のイメージとは異なる企業群が、実は長期的に最も高いリターンをもたらしてきたという事実です。
具体的には、S&P500のような主要指数を構成する企業の変遷、そして、業種別のリターンを詳細に検証しました。その結果、以下の驚くべき傾向が明らかになりました。
-
「時代を象徴する革新的な企業」や「成長著しい人気セクター」が、必ずしも高いリターンをもたらすとは限らない。 例えば、20世紀初頭には鉄道株、その後は自動車株、ラジオ・テレビ株、そしてITバブル期のハイテク株など、常に「時の花形」と呼ばれるセクターや企業が存在しました。しかし、これらの花形株が、期待された通りのリターンを投資家にもたらしたかというと、必ずしもそうではなかったのです。
-
むしろ、地味で「退屈」に思えるような伝統的な産業の企業、特に生活必需品や公益事業、食品・飲料、医薬品といったセクターの企業が、長期的に見れば市場平均を上回る、あるいは安定したリターンを上げてきたケースが多数存在することが示されています。これらの企業は、爆発的な成長こそ見せないものの、安定した需要があり、堅実な利益を上げ、そして定期的に配当を支払う能力に長けているという特徴があります。
この事実は、私たちが「未来の成長」に過度な期待を抱きがちな投資心理に一石を投じるものです。
「成長株投資」の落とし穴:なぜ多くの人が失敗するのか?
「次のAmazonを探せ!」「将来的に株価が10倍になる銘柄を見つけよう!」――このような刺激的な言葉に惹かれ、高い成長が期待される企業の株に投資する成長株投資は、多くの投資家にとって魅力的に映るでしょう。確かに、成功すれば大きなリターンを得られる可能性を秘めています。しかし、シーゲル教授の研究は、このアプローチに潜む深遠な落とし穴を明らかにしています。
その落とし穴とは、大きく分けて以下の2点です。
-
期待の織り込みと過剰評価: 多くの投資家が高い成長を期待する企業の株価は、その期待がすでに「先取り」されて、非常に高い水準にまで押し上げられていることがほとんどです。つまり、期待通りの成長を遂げても、株価はすでにその成長を織り込んでいるため、それ以上のリターンが得られない、あるいは、わずかな期待外れで株価が大きく下落してしまうリスクを抱えています。
-
競争と成功の難しさ: 新しい技術やサービスは、確かに世の中を大きく変える可能性を秘めています。しかし、その技術やサービスが本当に市場を独占し、圧倒的な利益を上げ続けることができるか、そして、後から参入する競合他社に打ち勝つことができるかを見極めるのは非常に困難です。多くの企業が淘汰され、わずかな企業だけが成功を収めます。その「わずかな成功企業」を事前に正確に予測することは、まさに「砂漠で針を探すようなもの」であり、並大抵のことではありません。
結果として、成長株投資は「ホームラン狙い」になりがちで、多くの打席で空振りに終わる可能性が高いのです。
「バリュー株投資」の優位性:地味でも確実にリターンを生む戦略
成長株投資の「不都合な真実」と対照的に、シーゲル教授がデータに基づいてその優位性を示すのが、バリュー株投資です。バリュー株とは、企業の本質的な価値(資産、利益、配当など)に対して、株価が市場から割安に評価されている銘柄を指します。
バリュー株投資の根底にある考え方は、ウォーレン・バフェットのような著名な投資家も実践しているもので、「優れた企業を適正な価格で買う」あるいは「良い企業を安く買う」というものです。具体的には、以下のような特徴を持つ企業に焦点を当てます。
-
安定した事業基盤と収益力: 流行に左右されにくい安定したビジネスモデルを持ち、堅実に利益を上げ続けている企業。
-
株価が過小評価されている: 何らかの理由で一時的に株価が低迷しているものの、企業としての本質的な価値は損なわれていない企業。
-
安定した配当支払い: 利益を株主に還元する姿勢があり、定期的に配当を支払う実績のある企業。
バリュー株投資は、爆発的な株価上昇を狙うものではありません。むしろ、市場に過小評価されている企業を見つけ出し、その価値が市場に認められるまで、あるいは安定した配当収益を得ながら辛抱強く保有し続けることで、長期的に堅実なリターンを狙う戦略です。地味に思えるかもしれませんが、感情に流されず、冷静に企業の価値を見極めることで、着実に資産を築き上げていくための、非常に強力で実績のある武器となり得るのです。
賢い投資家が実践する「負けない投資術」
これまでの章で、株式投資におけるリターンの源泉や、過去のデータが示す「不都合な真実」について見てきました。では、これらの知見を踏まえ、賢い投資家は具体的にどのような投資術を実践しているのでしょうか?シーゲル教授は、データに基づいた「負けない」ための具体的な戦略を提示しています。

市場平均を上回るための「簡単な」方法:パッシブ運用とコスト
多くの投資家は、「市場平均を上回る」ことを目標に掲げ、個別銘柄の選択や売買タイミングの予測に多大な時間と労力を費やします。しかし、シーゲル教授は、ウォール街のプロのファンドマネージャーでさえ、手数料(運用報酬や売買手数料など)を差し引くと、長期的に市場平均をコンスタントに上回り続けるのがいかに難しいかを、膨大なデータで実証しています。
そこで本書が強く推奨するのが、パッシブ運用、すなわち特定の市場指数(例えば、米国のS&P500や全世界株式指数など)に連動することを目指すインデックスファンド(ETFを含む)への投資です。
パッシブ運用の主なメリットは以下の通りです。
-
低コスト: アクティブファンドに比べて運用手数料が非常に低いのが特徴です。長期投資において、このコストの差は最終的なリターンに大きな影響を与えます。
-
効率的な分散投資: インデックスファンドは、指数を構成する多数の銘柄に分散投資するため、個別の銘柄リスクを大幅に低減できます。これにより、特定の企業が破綻してもポートフォリオ全体への影響は限定的になります。
-
手間がかからない: 個別銘柄の分析や売買タイミングの判断に時間や専門知識を費やす必要がありません。市場全体が成長する恩恵を享受できるため、忙しい個人投資家にとって、最も合理的で「簡単な」市場平均に近づく方法だと本書は示唆します。
「市場平均を上回る」という目標は、多くの人にとって魅力的ですが、そのための最も確実な方法は、実は「市場平均そのものに投資する」ことだったという、逆説的な真実がここにあります。
感情に流されない投資:人間が陥りやすい心理的バイアスとその対策
株式市場は、投資家の感情が渦巻く場所でもあります。市場が好調な時は「もっと上がるはずだ」と過度な楽観主義に陥り、逆に株価が下落すると「もっと下がるのではないか」とパニックに陥って狼狽売りしてしまう…これは、プロの投資家でさえ陥りやすい人間の心理的バイアスです。シーゲル教授は、こうした感情的な行動が投資リターンに与える悪影響を具体的に指摘し、それに対処することの重要性を強調します。
代表的な心理的バイアスとその対策は以下の通りです。
-
群集心理(ハーディング): 周りの投資家が買っているから自分も買う、売っているから自分も売る、といった行動に流されてしまう傾向。
-
対策: 他人の意見やSNSの流行に安易に飛びつかず、常に自身の投資計画と企業のファンダメンタルズ(基礎的価値)に基づいて判断する訓練をすること。
-
-
損失回避性: 利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛をより強く感じる傾向。これが、小さな損失が拡大する前に損切りできない、あるいは含み損を抱えた株をなかなか売却できない原因となる。
-
対策: 事前に損切りルールを設定し、機械的に実行すること。また、長期投資では一時的な含み損はつきものであると割り切る心構えを持つこと。
-
-
確証バイアス: 自分の考えを裏付ける情報ばかりを収集し、反対意見や不利な情報を無視してしまう傾向。
-
対策: 常に多様な情報源から情報を収集し、自分の意見とは異なる視点にも耳を傾けること。
-
これらの心理的バイアスに対処するためには、以下の実践的な行動が有効です。
-
投資計画の確立: あらかじめ自身の目標(いつまでに、どれくらいの資産を形成したいかなど)と、それに合わせた投資戦略(どのようなアセットアロケーションで、どの銘柄に、どれくらいの頻度で投資するかなど)を明確に定めておく。そして、市場の状況に左右されず、この計画に基づいて行動する。
-
長期的な視点の維持: 日々、あるいは月単位の株価変動に一喜一憂せず、数年、数十年といった長いスパンで物事を捉える。短期的な「ノイズ」に惑わされず、企業の長期的な成長と配当に焦点を当てる。
-
定期的な積立投資(ドルコスト平均法): 株価の上げ下げに関わらず、毎月決まった金額を定期的に投資することで、購入単価を平準化し、高値掴みのリスクを分散できます。これは感情を排除し、機械的に投資を継続する上で非常に有効な戦略です。
分散投資の本当の意味:リスクを抑えながらリターンを最大化する
「卵は一つのカゴに盛るな」という投資の格言は、多くの投資家にとって馴染み深いものでしょう。しかし、シーゲル教授は、単に多くの銘柄に投資するだけでなく、より深いレベルでの広範な分散投資の重要性を強調しています。
分散投資の本当の意味とは、以下の多角的な視点からリスクを管理し、同時に長期的なリターンを安定させるための戦略です。
-
銘柄の分散: 特定の企業の業績悪化や不祥事がポートフォリオ全体に与える影響を軽減します。
-
業種の分散: 特定の産業が不況に陥ったり、技術革新によって陳腐化したりするリスクを軽減します。例えば、ITセクターだけでなく、食品、医療、エネルギー、金融など、多様な業種に投資することで、バランスの取れたポートフォリオを構築します。
-
地域の分散: 特定の国や地域の経済状況、政治リスクがポートフォリオ全体に与える影響を軽減します。例えば、米国株だけでなく、欧州株、新興国株など、地理的に分散することで、グローバルな経済成長の恩恵を享受できます。
-
資産クラスの分散: 株式だけでなく、債券、不動産、コモディティなど、異なる値動きをする資産クラスに分散投資することで、市場全体の変動リスク(システムリスク)を軽減します。一般的に、株式と債券は逆相関の関係にあることが多いため、両方を組み合わせることで、リスクを抑えつつリターンを安定させることが期待できます。
広範な分散投資は、個別のリスクを吸収し、不確実な未来において、最も確実性の高いリターンを得るための、いわば**「守りの攻め」**の戦略なのです。
未来を予測するより、原理原則を理解する
投資の世界には、常に「次は何が来るか?」「どの企業が次の波に乗るか?」といった未来予測の誘惑が付きまといます。しかし、シーゲル教授は、この未来予測の罠に鋭く警鐘を鳴らします。なぜなら、未来を正確に予測することは、ほとんど不可能に近いからです。

経済成長と株価の関係:幻想と現実
私たちは、直感的に「国の経済が成長すれば、その国の株価も必ず上がる」と考えがちです。GDP(国内総生産)が伸びている国には投資妙味がある、といった見方も一般的でしょう。しかし、シーゲル教授は、驚くべきことに、国の経済成長率と株式市場のリターンには、必ずしも強い相関がないことを膨大なデータで示しています。
例えば、過去には、中国やインドといった急成長を遂げた新興国市場の株式が、成熟した先進国市場の株式よりも高いリターンを上げるとは限らないケースが多数ありました。これはなぜでしょうか?
その理由の一つに、**「期待の織り込み」**があります。経済が急成長すると予測される国の株式は、その成長がすでに株価に高く織り込まれていることが多いのです。そのため、たとえ経済が予測通りに成長したとしても、株価はそれ以上に上昇せず、期待外れに終わる、あるいはわずかな期待外れで株価が大きく下落するリスクを抱えています。
重要なのは、経済全体の成長以上に、企業の利益成長と、その利益から株主に還元される配当、そして株価評価の適正さであると本書は強調します。つまり、国のマクロ経済の成長率を予測することよりも、個々の企業が持続的に利益を上げ、株主価値を高めることができるかを見極めることの方が、投資においてははるかに重要であるということを示唆しているのです。
イノベーションが投資に与える影響:新技術への過度な期待に注意
歴史を振り返れば、蒸気機関、鉄道、自動車、電話、ラジオ、テレビ、コンピューター、インターネット、そして最近ではAIやバイオテクノロジーなど、常に新たなイノベーションが世界を大きく変えてきました。私たちは、こうした革新的な技術が、必ずその発明に関わった企業や、その技術に最初に乗っかった投資家に莫大な富をもたらしたと信じがちです。
しかし、シーゲル教授のデータは、ここにも「不都合な真実」が存在することを明らかにしています。例えば、自動車産業が誕生した初期には、数えきれないほどの自動車メーカーが乱立し、その多くは淘汰されていきました。インターネット黎明期にも、多くのドットコム企業が生まれましたが、結局生き残ったのはごく一部です。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
-
激しい競争: 新しい技術や市場には多くの企業が参入し、激しい競争が繰り広げられます。これにより、価格競争や研究開発費の増大などで、企業の利益が圧迫されることがあります。
-
期待の先行: イノベーションに対する過度な期待が株価に先行して織り込まれ、企業がその期待に応えられなかった場合に株価が大きく下落することがあります。
-
消費者の恩恵: イノベーションは、企業よりもむしろ、その技術やサービスを享受する消費者により大きな恩恵をもたらすことが少なくありません。例えば、インターネットの恩恵を最も大きく受けたのは、インターネットを利用したサービスを展開した企業だけでなく、そのサービスによって生活が豊かになった私たち消費者全体です。
シーゲル教授は、「イノベーションそのもの」と「それによって生み出される投資リターン」を混同してはいけないと強く訴えます。むしろ、そのイノベーションによって恩恵を受ける、あるいはイノベーションの影響を受けにくい、地味だが安定した既存企業に目を向けるべきであると示唆しています。例えば、スマートフォンが普及しても、スマートフォンの部品を提供する企業や、スマートフォンで使われるアプリから安定的に収益を上げる企業の方が、革新的なデバイスそのものを生み出した企業よりも安定したリターンを上げてきたケースもあるのです。
投資戦略の「成功と失敗」を分けるもの
最終的に、投資戦略の成功と失敗を分けるのは、未来を正確に予測する**「予言者」のような能力ではありません。それは、以下の普遍的な原理原則を理解し、感情に流されることなく、ひたすら愚直に実践し続ける能力**です。
-
長期的な視点を持つこと: 短期的な市場のノイズに惑わされず、数年、数十年単位で企業の成長と配当に焦点を当てる。
-
配当の再投資効果を理解すること: 複利の力を最大限に活用し、配当を新たな投資に回すことで、資産の雪だるま式増大を狙う。
-
感情に流されず、規律を保つこと: 投資計画を立て、それを機械的に実行する。市場が暴落したときでもパニックにならず、冷静に買い増しを検討できる精神力を養う。
-
コストを徹底的に意識し、効率的な運用を心がけること: 低コストのインデックスファンドを活用し、無駄な手数料や税金を最小限に抑える。
-
広範な分散投資を行うこと: 銘柄、業種、地域、資産クラスを多角的に分散することで、予期せぬリスクからポートフォリオを守る。
これらは決して派手な戦略ではありません。むしろ、地道で退屈に思えるかもしれません。しかし、シーゲル教授が膨大なデータで示した「真に有効な」アプローチであり、多くの投資家が感情や流行に流されて失敗する中で、着実に成功を収めるための唯一とも言える道なのです。
要約:あなたも「賢い投資家」への一歩を踏み出そう
ジェレミー・シーゲル教授の『株式投資の未来』は、投資の常識を覆し、私たちが抱きがちな誤解をデータで粉砕する、まさに目から鱗が落ちる一冊です。短期的な相場変動に翻弄され、誤った情報に踊らされがちな現代の私たちに、長期的な視点と、科学的なデータに基づいた冷静な判断の重要性を改めて教えてくれます。

この不朽の名著から学ぶべき、賢い投資家になるための最も重要な教訓は、以下の3点に集約されます。
-
配当と再投資の力を決して過小評価しないこと。 多くの人がキャピタルゲインばかりに注目しがちですが、長期的な株式リターンの大部分は、地道に支払われる配当金と、それを再投資することで生まれる複利効果によってもたらされます。配当を「おまけ」と捉えるのではなく、資産成長の重要なエンジンと認識し、再投資を愚直に続けることが、将来の大きな実りを約束します。
-
人気や流行に惑わされず、企業の「真の価値」と「適正な株価」を見極めること。 時代の寵児ともてはやされる成長株や、特定のテーマ株に飛びつくのは魅力的ですが、その裏には過度な期待による株価の過熱や、激しい競争による失敗のリスクが潜んでいます。むしろ、派手さはなくとも、安定した利益と配当を出すバリュー株に注目し、冷静に企業のファンダメンタルズを見極める視点が、長期的な成功には不可欠です。
-
感情に流されず、低コストで広範に分散されたインデックス投資を継続すること。 市場の上げ下げに一喜一憂し、感情的な売買を繰り返すことは、リターンを大きく損なう原因となります。個別の銘柄選択やタイミング投資の難しさを認識し、手数料の低いインデックスファンドを通じて、市場全体に広範に分散投資し、愚直に積立投資を続けること。これこそが、多くの個人投資家にとって、市場平均を上回り、着実に資産を形成するための最も確実で再現性の高い道であると本書は力説しています。
賢い投資家への道は、決して複雑な魔法や秘密のテクニックを学ぶことではありません。それは、データに裏打ちされた普遍的な原理原則を理解し、自身の感情をコントロールしながら、粘り強く、規律正しく実践し続けることに尽きるのです。
今日からあなたも、「株式投資の未来」が示す普遍の教訓を胸に、自身の投資スタイルを見直し、より確固たる信念を持って資産形成に取り組んでみませんか?それは決して難しいことではありません。感情をコントロールし、長期的な視点を持ち、データに基づいた普遍的な原則を信じること。これこそが、あなたの資産を真に豊かなものにするための、最も重要なカギとなるでしょう。
もしこの記事を読んで、さらに深く学びたい、具体的なデータに触れたいと感じた方は、ぜひジェレミー・シーゲル教授の『株式投資の未来~永続する繁栄への投資戦略』を手に取ってみてください。きっと、あなたの投資人生に大きな変革をもたらすはずです。
バリュー投資関連の本は賢明なる投資家やバフェットの銘柄選択術なども有名なのでぜひこちらもご覧ください。
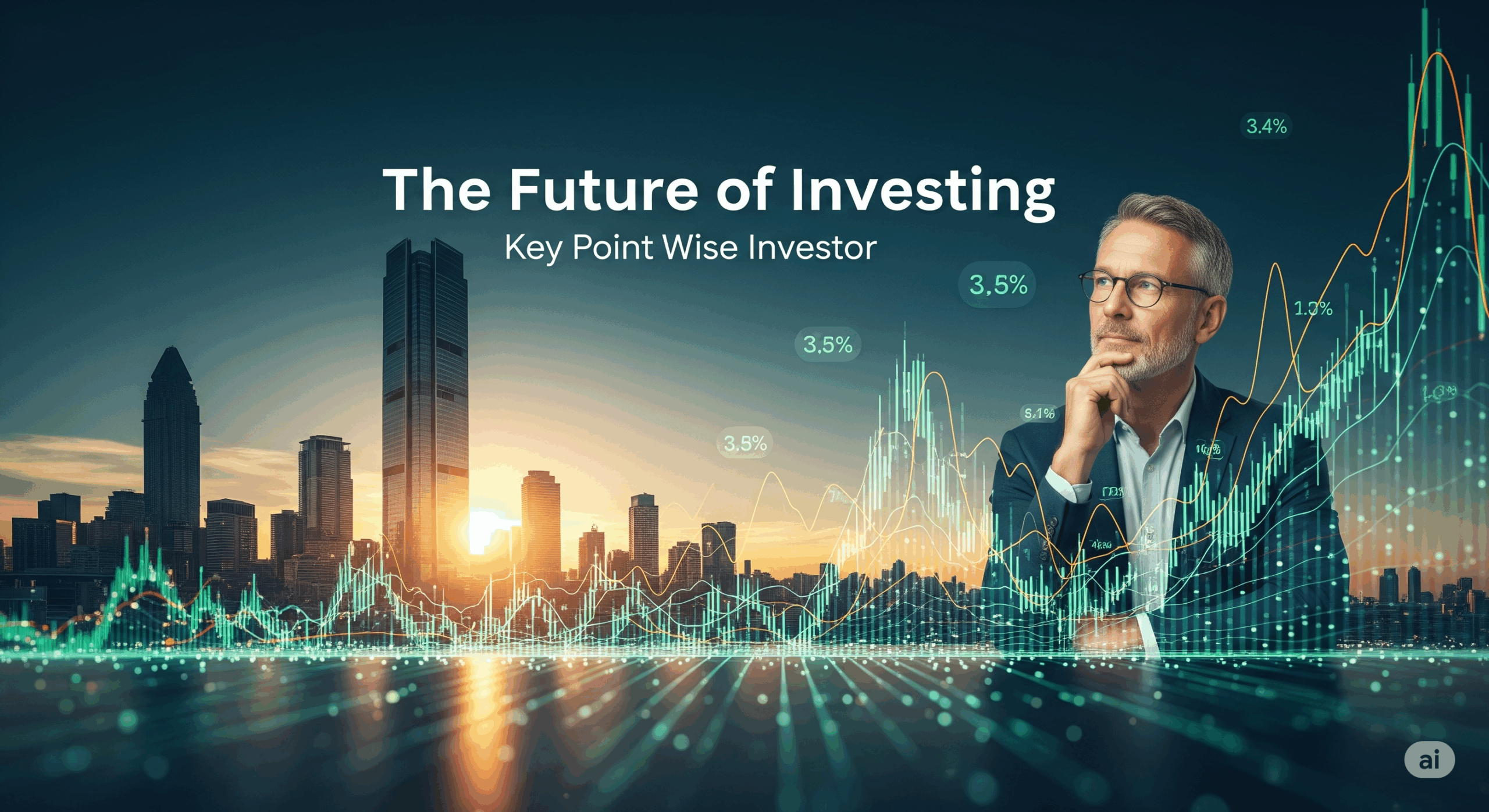
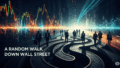
コメント